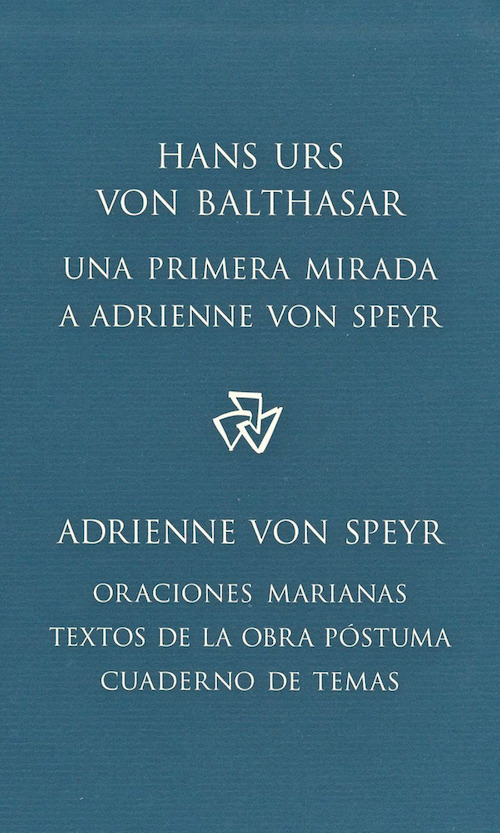メニュー
日常生活における聖性
ある人が朝仕事に向かっています。何も考えずにいると、突然通りから、ヒット中のメロディが流れて来ます。それを耳にして聴き続けると、ついにはそのメロディはその人につきまとい、一日中その人はそれを頭から追い払うことができなくなってしまいます。あるいはまた、たまたま耳にした悪い言葉が、自分に関係あるかどうかさえも分からないのに、心に引っかかり、延々と考え込んでしまうことがあります。もしかしたら、車のドアがバタンと閉まった瞬間にその言葉が聞こえて来て、一日中似たような音を聞く度に、その言葉がまた頭に浮かんで来るかもしれません。
私たちの精神生活は、常にどこか無防備にさらされた状態で、外的な影響や刺激に捉えられたり、形成されたり、整えられたりするものです。そしてほとんどの人々の場合、日々の仕事はその全神経を捉えたり、夢中にさせたりするものではなく、彼らの内には内面的生活のための完全な空間が、未使用のまま残されているものです。メロディや考えが頭から離れなくても、それが日中、仕事の妨げになるわけではありません。たとえその人自身は、自分はもっと集中して、もっと仕事に打ち込めるはずだという意識を持っていたとしても、その人が仕事中に気が散っていたとか、集中していなかったとか、あるいは、その日の仕事をこなす際にどんな気分でいたか、どんな固定観念が頭から離れなかったかなどということを、仕上がった仕事自体から見て取れる人は誰もいないでしょう。しかしおそらく、その人自身がその両日――とあるメロディが頭から離れなかった日と、とある悪い言葉が頭から離れなかった日――のことを振り返ってみた時、自分の個人的内面世界がこれほどまでに偶然に影響されていたのかと、驚くことでしょう。そして、その人は自問することになります――人は、そのような些細なことで影響されたり事を決められたりするのではなく、隠れていても身になるような栄養によって生きることはできないものだろうか、そして、内なる選択と決意によって生き、目に見えずとも日常生活を通して同伴してくれて、自分の人生を本質的で、キリスト的で、聖なるものにしてくれるような源によって生きることができないものだろうかと。(メロディや考えのような)取るに足らないものですら、既にそれほどの力を私たちの上に及ぼすとすれば、いや、むしろ、私たち自身がそれほどの力を持っているとすれば、つまり、日常生活で未使用の深い内面空間を持っていて、その完全に空いた空間を日常生活の取るに足らないことに利用できるのだとすれば、このような自由な可能性を、真の現実、すなわち、神の現実に対して提供するような生活はどのようなものになるでしょう。
私たちはキリスト者です。私たちには信仰があります。教会が最低限求めることは満たそうとします。それでも、もしかすると、私たちも、上述の人が仕事をこなすような仕方で、それをただこなしているだけかもしれません。きちんと、忠実に、非の打ち所がなくこなしているには違いなくとも、内面には空っぽな空間があるものです。もしかしたら、そこは「教会の義務」が占める空間よりも非常に大きくて、そこを、私たちは自分自身のために生きるための、自分自身でしつらえた空間として確保しているかもしれません。しかしもし、私たちの中で今は偶然や瑣末な楽しみにふさがれている場所が、神の御言葉によって占められたらどうでしょうか。神の御言葉は、この場所の所有を主張してきます。神の御言葉は、私たちの中で、神の種が聖母マリアの中で生きたように生きることを望んでいます――つまり、すべてを支配しながら、育っていくことを。もし、私たちの魂の、いわば扉を御言葉に対して閉ざしてしまうのであれば、つまり、もし留保をつけるなら、私たちは信者やキリスト者を名乗るべきではありません。あるいはもし、私たち自身の一部しか御言葉に委ねないなら、私たちは信者やキリスト者を名乗るべきではありません。信仰とは、御言葉を運ぶ者になることであり、それはひいては、自分自身を完全に、ますます一層、御言葉によって運んで頂くことを意味するのです。
信仰とは、神の御言葉にゆっくりと、連続的に、段階と間隔を測って近づいていくことではありませんし、何かよく考えられた計画に従って段々と神の御言葉に向かって立ち返ることでもありません。信仰とはまた、より簡単そうなキリストの御言葉をまず試してみて時間を稼ぎ、すべてを要求してくるような、より難しい御言葉に挑戦するのは不確定の後日に回すというようなことでもありません。むしろ信仰とは、直ちに思い切って全体に手をつけること、最も信じ難い、最も解釈不能な言葉ですら、即座に自らの内に受け入れ、肯定することなのです。そして、突然、絶対的なものにいやが応でも対峙して、いやが応でもこの絶対的で「不可能なもの」に、要求された場所を明け渡すことです。その場所は、道端で起こるあらゆる偶然に対して無頓着にぼんやりと開かれていることとは、もはや何の関係もありません。その場所は、私の中の内なる場所となり、そこから私の魂における他のすべての場所や空間が占められ、秩序づけられるようになるのです。そのような状態に導いてくれる御言葉は、例えば、次のような主の御言葉かもしれません――「あなたがたの天の父が完全であられるように、あなたがたも完全な者となりなさい」(マタイ 5:48)。あるいは旧約における神の御言葉もそうでしょう――「あなたたちは聖なる者となりなさい。あなたたちの神、主であるわたしは聖なる者である」(レビ 19:2)。つまりそれは、私たちの日常生活全体を、そのあらゆる些細な事柄も含めて、神の祝福の中に投じ、私たちの罪の惨めさ、あらゆる種類の私たちの不完全さを御父の聖性の中に沈めよ、という要求です。つまるところ、私たちの中に、私たち自身ではなく神のための場所を作れ、ということです。
この一見不可能な事を要求するのは、父の御心というただ一つの御心を知る、神の子です。彼は、生涯、この御心を実現すること以外のことは何もしませんでした。彼は、人となり、御父の永遠の1日で満たすために、私たちの日常をその身に担いました。彼は、天上から地上に降りて来て、自分の永遠性から時間性をつかみ、それを衰えず、暗くならず、妥協のない、永遠の命の器としました。神の尊厳全体が、この自己卑下に含まれています。神はこうすることで何も失うことはありません。父なる神が聖なる方であるように、神の子は人としても聖なる方です。「あなたたちのうち、いったいだれが、わたしに罪があると責めることができるのか」(ヨハネ 8:46)。神の子は完全さを生き、それによってその完全さが私たちのために開かれます。彼は、信じ難い事を成し遂げることで、ご自分と一緒に、逆方向にそれを成し遂げるよう、私たちを招きます――つまり、下から上に向かって、御父の聖性によって特徴づけられる聖性の中へと、私たち自身を投じるように。それは、私たちが個人的な性質と使命に従って、その聖性を生きるためです。
このように飛躍して身を投じることは、何よりもまず信仰による行為です。「神のように完全であれ」という、御子のこの要求をいくらかでも理解しようとすれば、それは純粋に合理的な意味や純粋に理論的な意味で外から見た場合には不可能だ、ということは直ちに明らかでしょう。そのような要求は、神について、また被造物について、さらには罪びとについて、それが何かを知っている理性にとっては、まったくばかげたことです。私たちが純粋に理性的に、自分たちが何者かを吟味し判断するなら、私たちがこの要求を満たすことができないのは明々白々です。もちろん、私たちが主を嘘つき呼ばわりしたくなければ、主が求めることは可能です、と言うより他ありません。主の力によって私たちの中で実行される動きや働きにおいて、私たちは本当に主にそのように実行して頂くように振る舞い、従ってまた、特に、私たち自身の理解や測定の基準を無条件に断念します。どの信者も、自分自身の聖性を見たり、理解したり、主張したりすることは決してできませんが、それと同様に、その自分自身の中で神がご自分の御言葉を実現することができないなどと主張することも、信仰においては許されません。信者は洞察力と理解力を神に委ねるものです。聖性とは言葉であり、その真理は神においてあります。信者においては、それは要求という形においてのみ生きるのです。信者は、自分の人生を「聖なる者であれ!」「完全であれ!」などの要求というモットーの下に据えることができます。しかし、その要求が達成されたとみなすことは決してできません。そして究極的には、信者にはこの要求を受け入れるかどうかの自由はまったくなく、ただそうするより他ないのです。信じることによって、信者は、自分の人生を神が採択した真理の下に据え、その真理に仕える用意があると宣言するのです。ゆえに、聖性の根源は従順です。
信仰の従順、それはまさに盲目的な従順であり、そのような従順は最深のところで知っているのです――人間的力で見られるもの、考えられるもの、理解できるものは、ここには何もないと。そしてそれはまた、不条理で自暴自棄な信仰でもありません。そのような信仰は、実は密かに、神よりもよく知っているつもりになっているからです。むしろ本当に従順な信仰とは、謙虚で、開かれた信仰であり、なるようになるという希望に最大限の空間を託すものです。それは主の奇跡のようなものです。私が生まれつき半身不随だとして、主が私に「立ちなさい!」と言えば、私は立ち上がります。それは、私の理性が自ら上に向かって努力して、信仰の正しさと合理性を理解するまでに至ったからではなく、むしろ私が、神の御言葉を自らの内に受け入れ、その御言葉の命令によって、信仰を受けるからです。それはまったく突然にであり、命じられたことを成し遂げるために自身の信仰が十分かどうかなどと吟味することもないのです。ただ主がその命令において私に与えてくださる信仰の贈り物を、途切れることなく受け入れるだけです。立ち上がるための力は、「立ちなさい!」という、その言葉を信じることにあるのです。立ち上がることの意味や、その過程に関わるすべてのことが、この言葉に含まれているのです。私は、ただ二歩だけ進んで三歩目はもう無理だ、という状態になるために立ち上がるのではありませんし、再び横になるために立ち上がるのでもありません。立ち上がるということは、歩けるということであり、そのことを含むのです。立ち上がる私は、立ち上がる力を使い果たすのではありません。「立ちなさい!」という要求は、立ち上がったという行為の中に留まり、立ち上がるための力もまた然りです。つまり、私は明日もまた立ち上がるでしょうし、要求がされる度に毎回立ち上がるでしょう。その要求は、立ち上がり、立ち上がるという行為に留まる、という生きた状態を作り出したのです。日常生活においても、主は、奇跡を起こす言葉と何ら変わらない力を持つ言葉を与えてくださいます。その言葉には常に今、命が宿っており、その言葉を受け入れた者は、今を生き、御言葉に仕えることができますが、それに際して、仕える者からはすべての段階づけや、近さや遠さに関するあらゆる判断が取り上げられます。御言葉は絶対であり、仕える者は自分の中でそれを相対化する権利を持たないのです。
相対化は、必然的に不信仰の始まりか、少なくとも薄い信仰に通じ、相対化すると、主の要求を、誇張された実現不可能なこととみなすようになります。私自身が不完全であることは――仮に私が最悪の罪びとであったとしても――ここでは全く関係のないことです。御言葉がそのためにその絶対性から降りるということはないのです。御言葉は弱まることはなく、絶対的に生きるもの、生きた絶対的なものであり続けます。不信仰による拒絶は、御言葉の絶対性を奪うことはできません。しかし、信者に求められるのは、自分の命を、自分の中の御言葉の命に委ねることです。それによって、御言葉がそれ自体において持っている力が、その信者の中でも発揮されるようになるのです。
私たちはヒットメロディを耳にしながら1日生活できるのです。同じことを主の御言葉で試してみてもよいでしょう。そうすれば、メロディよりもはるかに強力な主の聖性が、私たちに最も強烈な仕方でつきまとうでしょう。メロディは美しくとも、やがて消耗し、陳腐になり、耐え難くなるものです。しかし主の御言葉は、常に今、新鮮な状態で、神の口から出て来ます。そして、私たちはその御言葉をこれほど近くに、これほど切実に、これほど永遠に、消耗することもなく、常に新しく、受け取ることができるのです――その御言葉の不可解さも含めて。なぜなら、誰が一体、御父の完全さを推測することができるでしょう。それを知っているのは御子と聖霊だけです。それでもなお、私たちはその完全さの中に入るべきであり、そしてそれを相対化してはならないのです。もし私たちが御父の聖性を、私たちに到達可能で理解可能なものに照らして測ろうとしても、そしてもし、私たちが御父の聖性を想像するために、この世のすべての価値と完全性とを足し合わせて、それを無限大に引き上げ、「これが御父だ!」と言いながら、「そして、これよりさらにもっと偉大なのだ!」とため息混じりに付け加えたとしても、私たちは常に、神の完全さを軽んじる危険にさらされています。なぜなら、私たちの有限な認識方法においては、神の完全さはあまりにも簡単に、人間的で世俗的な小さな長所の無限連鎖のようなものになってしまい、そうなると、真にそれを区別する唯一の性質、すなわち、絶対的で神的な性質が奪われてしまうからです。そしてもし、私たちがそのような計算に基づいて行動しようとし、無数の小さな、些細な行為や美徳をいくつも積み重ねることによって、ゆっくりと神の完全さへと向かい、徐々に御子の要求を満たすことができるなどと考えたとしたら、私たちが確実に達成したことになるのはただ一つ、すなわち、私たちの人生における絶対的なものを殺すことです。
信仰によって善を行う人は、常に告白しなければなりません――「それは、私に依拠する限り、何も重要なことではなく、考慮に値しない」と。そのように重要でないことを足し合わせて、その結果として最終的に何か偉大なことを証明しようとすることは、理性に反するだけでなく、信仰に反することになります。私たちは、目に見えない信仰の神秘を、目に見えるこの世の支配可能な事実の中に見出したい、などと思うべきではありません。従って、私たちにできることはただ一つ、常に自分の全存在を絶対的要求の中に置き、常に自分のすべてをもって神の御言葉を受け取ろうとし、その要求の結果として、主が形成する答え全体を待ち望むことです。待ち望むことは信仰の行為であり、それはそれ以上に分解できるものではありません。完全であれという命令は、あらゆる段階づけを破壊します。私たちのすることは、それが人間として経験可能なことである限り、言いようのないほどわずかです。決定的なのは、御父のように完全であれという主の要求だけです。もし私たちが、自分のわずかな行為を一々重要であるかのように吟味するなら、私たちの行為は私たちと主の御言葉との間の障害となってしまいます。私たちが善行と認識し評価する行いをすればするほど、障害は高く積み重なり、私たちは主の御言葉を分解せずに受け入れること、つまり、信仰において受け入れることができなくなります。善、私たちが善と考えていることでも、悪や罪と同じように、私たちが神の元に行くのを妨げることがあり得るのです。
その溝を飛び越える全可能性は、御子にあるのです。御子は、自らの愛によって、世を御父の元に導き戻すために、この世に来られたのです。人となることで、御子は神としての存在も神としての知識も失いませんでした。むしろ、御子の任務全体が愛の任務であり、それはそれを実行する行動だけでなく、それを表象する観想においてもそうでした。御子はまた人としても御父を直視しますが、その使命を果たす間、その直視はその使命から孤立したものではありません。その直視は、ただ御子が自分を元気づけるために利用する何らかの個人的特権ではなく、むしろ御子の愛の使命の中にその尺度と意義を持つのです。御子は御父を知っており、子としての愛において、御父の完全さを見ています。御子の直視は行為というよりもむしろ状態であり、それは御子の愛と従順による千里眼のようなものです。ゆえに、御父への愛において、御子は神と人間との間の尺度を確立し、両者の間に橋を架けます。御子は御父を世に合わせるのではなく、絶対的な父を世に対して示すのです。そして御子は、人が神の期待通りに生きることは可能であることを、ご自分の生涯によって証明しています。それは、絶対的な父への愛に生きる、生き方です。御子が人として完全であるのは、御父への敬意です。それによって御父の天地創造の正しさを示すからです。しかし、御子の完全さは、御父と人類への御子の愛の行為であり、成果です。御子の愛はあまりに偉大なので、御父の聖性を人間の姿において生きることができるのです。
御子は、日常世界の喧騒から遠く離れ、静かな敬虔の時間において繰り広げられるような聖性を生きているのではありません。御子の聖性は、その人生のあらゆる状況において、常に同じです。御子の聖性は、常に御父と同じなので、自分自身と同じなのです。そして、それは、常に御父の愛から流れ出して、御父の愛に還るがゆえに、御父と同じです。そして、御子は御父のこの聖性を、十字架の死の従順に到るまで人として生きるからこそ、その聖性を恵みのうちに人々に伝えることもできるのです。御子が人々にする要求はすべて、御子自身が前もって満たしたものであり、こうして満たしたことから、その要求を満たす力が与えられるのです。御子は常に、ご自分の言葉を御父に最も近いものとされます。御子の言葉においてほど、人が御父に近づける場所は他にありません。そして御子が「父のようになれ」と要求する時は、まるでその瞬間に人々を御父の腕に直接投げ込んでいるかのようです。御子は、自ら同時に御言葉でもある子として、架け橋となることによって、御父と人間との間の距離を無くするのです。
主の言葉はすべて、歴史的状況の中で語られており、それらの状況のほとんどを私たちは知っています。しかし、これらの言葉は常に、これらの状況を超えて有効です。なぜなら永遠なる状況は歴史的なものの中に輝いているからであり、なぜなら御子はこれらの言葉をずっと以前からご自分の本質の表現として携えておられ、そのどれも御父への永遠の愛と矛盾するものではないからです。主の言葉は、私たちが地上の人間として聞き取ることができるように、何らかの形で私たちの歴史性に適応していますが、私たちの時間の法則に適合しているのではありません。なぜなら、これらの言葉は私たちの時間を永遠へと吸収するからであり、時間の中で次第に消えたり、鈍化したりすることはないからです。主の御言葉は永遠の命です。なぜならそれは御子の御父への愛であり、すべてを御父の元へ導き戻すからです。
聖書という書物は、私たちがいつでも御子の永遠の御言葉に出会うことができる、日常的なものとなっています。しかし、私たちは聖書を読んでいる間だけその御言葉に出会うのではなく、御言葉は私たちの記憶に留まり、私たちの意志によっていつでも生きたものとなり得るのです。御言葉は、私たちの行動の尺度、私たちの現存在の入れ物となり得るし、ある意味では私たちの命よりも生き生きとした生命力を発揮することができます。御言葉は私たちを常に自らの内に取り込んで、保護してくれるのです――要求としてもそうですが、何よりもまずは、愛として。もしこの洞察が私たちの中で生きたものとなるならば、あらゆるものが私たちに完全な従順を試みるように迫る瞬間が訪れるでしょう。それはつまり、神のことをしばしば敬虔に考えるだけでなく、神の個々の戒めを守るだけでなく、むしろ、神の絶対的存在を私たちの生活の圧倒するほど近くに常に伴わせ、その中において愛を、そして愛の中において愛の要求を理解するということです。それはまた、理解できないという状態にあえて留まるということでもありますが(というのも、結局のところ、誰が絶対的なものを理解したいと望むでしょうか)、しかしまさに理解できないからこそ、神が私たちに期待する通りに留まる覚悟をし、そして、私たちの覚悟から完全さを形成して頂くよう神に委ねるということでもあります。
それからまた、教会における聖人たちの聖性というものがあります。彼らの聖性は、絶対的なものの中で動き、また動かされるということにあります。彼らは「十分」という言葉を知りません。彼らはまた、いかなる尺度も適用しません。彼らは神と絶え間なく対話し、そうすることで常に神から指示を受け、その指示はたとえ私たちにとっては必ずしも明白ではないとしても、とにかく常に神の御心を目標としているのです。ある意味、聖人たちの人生は、主の地上における生涯の継続のようなものです。聖人たちの人生は、詳細に語ったり、足跡をたどったりすることができるもので、多くの出来事から成り、個人的特色にも事欠きません。しかしそれでも、それらはすべて二義的なことです。第一義的で、唯一重要なことは、彼らの魂が神に向けられていることです。魂において神に働いて頂くのであり、それによって、他の残りのすべてのことは、唯一絶対の神の要求としてのみ現れてくるのです。神が地上で日常生活を送られたように、聖人たちもまた日常生活を送っています。しかし、彼らが真に聖人であるとすれば、それは彼らの日常生活が、最も非日常的な事柄の表現、すなわち、御父の永遠の命とそれにおける御父の御心の表現となったからです。聖人たちは、永遠の命の炎で燃えています。そして私たちが彼らを扱う時も、この炎を弱めてはなりません。私たちは聖人たちを過小評価してはなりません。私たちは聖人たちの日常生活をよく見るべしとされています。フランス、アルスの小教区1やリジューのカルメル会2を見ると、このような日常生活を送った人々の聖性をほとんど忘れてしまいそうになります。このような危険は避けるべきです。今日しばしば見られるような、聖人たちをいわば「人間化」する過程で、神が彼らにおいて教会と世に与えた賜物の偉大さを見落としてはなりません。聖人たちの日常生活を、彼らの神との関わり合いの只中に戻してみれば、異なる様相が見えてきます。こうすると、私たちには休息や日課のようにみえるものでも、実は、常に神からの働きかけであり、そしてその働きかけに委ねられることであると分かります。すると、私たちが見ているものはもはや、聖人の人生や聖人の魂、聖人の意識といった相対的な側面ではなく、むしろ計り知れない神の働きそのものなのです。日常生活とそれを満たすすべてのものは、別のもの、つまり聖人たちの本当の生活のための枠組みに過ぎず、それによって、私たちはこの理解し難いものを位置づけることができるのです。しかし、この位置づけですら、神を位置づけることはできないということを私たちに悟らせる限りにおいて、重要であるだけです。聖人たちは、ここ地上にいる時も、既に永遠の命において生きています。実際のところ、本当の聖性の敷居を跨いだ瞬間、彼らは既に天国に入る準備ができているのですから、実はもはや地上で生きる必要はないのです。それにもかかわらず彼らが地上で生き続けるとすれば、それは、他の人々のために一種の自発性をもって、ちょうど御子が地上での日常生活のすべてを自発的に送られたように、愛、犠牲、苦しみをもって彼らに奉仕するためであり、また、御子が私たちに神の道をすべて贈ってくださったように、他の人々に聖人の道(アッシジの聖フランシスコなら清貧の道、聖イグナチオ・デ・ロヨラなら従順の道、リジューの聖テレーズならば小さき道)を贈るためです。
聖人たちもまた、神の聖性の例示の一つに過ぎません。聖人たちの聖性は、一瞬たりとも神の聖性から切り離されて、それ自体のものとして考えられてはなりません。聖人たちは神の聖性によって生きているのです。そして、神の聖性は常に無限であるがゆえに、個々の聖人たちの聖性を互いに比較検討することは不可能です。聖性は神の中にあるがゆえに、常に一つで不可分なのです。それと同じく、神の聖性を私たちに示す御言葉と愛もまた、常に一つであり不可分なのです。人は上から、つまり、神自身から、神に近づかねばなりません。もし、下から神に近づこうとするなら、つまり、個々の有徳な行為をつなぎ合わせ、ある時点でそれを達成したものとして振り返るなら、椅子に上って太陽に手を伸ばす子どもと同じことをしていることになるでしょう。聖人たちですら、私たちにとっては、何よりもまず、梯子ではなく、しるし、すなわち、キリストが生きているというしるしです。聖人たちは、無条件にキリストの受肉と結びついています。彼らは啓示されたものであり、捧げられたものです。真の聖人たちにとって、地上の生活は苦痛でなくてはなりません。彼らは神を見たいという欲求に駆り立てられているからです。それでも、彼らは、従順から、地上に留まります。それゆえ、彼らは地上におけるキリストの従順に非常に近いのです。キリストと共に、彼らは日常生活を聖化します。彼らが能動的に日常生活を聖化するのは、彼らの日常生活が、観想から流れ出る行動という意味で、受動的に聖なるものだからです。聖人たちの生活は、御父に対する御子の愛の中の、愛の行為なのです。
御子は、この世を御父の元に返すために来られ、この行為によって御父に対する無限の愛を証明されました。しかし、御子はこの証明を独りですることは望んでおられません。御子はその証明を神として完全に行いますが、同時に、開かれたものとして、私たちを招いて行われます。まるで、ご自分のなさることが、ご自分だけの行為ではなく、むしろ同時に絶対的に、ご自分のエウカリスティア的存在と意志のしるしであるかのようです。御子が望まれるのは、父なる神が、贖われた人々の中に、ご自分への愛を認めるようになることです。だから、御子は信じる者にご自分の愛を贈られるのです。私たちは決して、御子のこの愛を完結したものとみなしてはなりません。さもないと、私たちは御子の愛の掟に背くことになるでしょう。御子が私たちを愛されるのは、私たちに愛を教えるためです。そしてこの愛は、御子自身の愛から生じ、それに匹敵する炎をもって、聖人たちにおいて生きています。こうして、私たちが聖人たちから聞き知り理解することは、常に繰り返し、御父と御子との間の愛を聞き知り、理解することとなりますが、それは決して美的な観想に留まることはできず、むしろ参加すること、立ち会うこと、御子と一緒に人類と御父を愛することを直ちに要求されるのです。日常生活で私たちが接することができる聖性とは、御子を通して、御父の完全さに愛をもって与るよう、私たちは招かれているということなのです。
アドリエンヌ・ フォン・シュパイア
原語タイトル
Heiligkeit im Alltag
読む
キーワード
書籍説明
言語:
日本語
原語:
ドイツ語出版社:
Saint John Publications翻訳者:
理矢子 彦田年:
2023種類:
論文
その他の言語